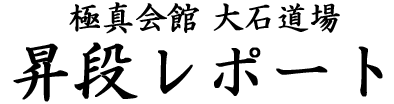|
この度は、二段の公認審査会を受ける機会を与えて頂いた大石代悟最高師範に心より御礼申し上げます。
二年前の昇段審査会で、自分の組手に納得がいかず悔いを残してしまいました。
今回の昇段審査会では、“強気で相手に立ち向かい、切れのある蹴りを出すこと”を目標に日々稽古に励みました。
稽古は仕事が終わってから、近所の公園や山や湖畔で夜の11時、遅いときには12時くらいから1〜2時間くらいを週2〜3回、
“型”を中心に、そのほか走りこみや“自然の立ち木”を相手に稽古、あとは道場での稽古を週1回と行っていました。
40歳を過ぎたころから、足の股関節がかなり硬くなり蹴りが以前にも増して出しにくくなりました。
これではいけないと週に1回は琵琶湖の浜に行き、砂浜で柔軟体操をやるようになりました。
琵琶湖での柔軟は夜の波のさざめく音と白い砂、すんだ空気が心地よく、自然の中で瞑想をしているかのように最高に気持ちの良いものでした。
その後に、近くにある鉄棒に手をかけてひとつひとつの蹴りを最初から基本通りに蹴れるようにフォームのチェックを繰りかえし行いました。
心の中で“蹴りというものは本当に難しい!”といつも痛感させられました。その後は“型”の稽古を繰り返しおこないました。
思えば、今から二年前に沼津本部道場で芹沢事務局長に“型”をご指導いただいた時に教えて頂いたお陰で、多くのことが昨日のことのように
頭の中でフラッシュ・バックされ、不思議なことに体もその時の事を覚えているもので、教えて頂いた通りに繰り返し繰り返し行いました。
スタミナ対策としては家の裏にあるK山の頂上まで3kmをダッシュでかけ上がりました。
途中、あまりの苦しさにスピードが落ちてしまうことありましたが、しばしば行いました。
ところで、私が稽古の中で最も好きな稽古の一つに“立ち木に、巻き藁を巻いてひたすら突く”というのがあります。
この巻き藁はゴムで木に巻きつける携帯巻き藁で5年前に頂いたものを“家宝”のように大事にしているものです。
これをしていると嫌なことも忘れ、心がスーッと楽になり無心になれ、不思議にプラスのパワーがわいてくるのです。
ある日の夜、K山のふもとで木を相手に巻き藁を突いていたら茂みの中から四つの目がこちらをじっと見ているではありませんか。
いくら心霊スポットで有名な場所とはいえ、幽霊の存在を全く信じない私にとってはこの場所は誰も来ない絶好の稽古場所でした。
この場所では以前にも、木を蹴っている時に「ガサガサッ・・」と大きな音がして、背筋が凍るような恐怖を覚えたこともありました。
翌日、そのことを家内に話すと「そんなのタヌキかイタチでしょう」と一笑に付されました。それが・・・、まさか・・・。
勇気を出して茂みの方に鋭い眼光を作り、恐怖に襲われながらも、そちらの方にゆっくりゆっくりと近づいていくと、茂みの中には
何と1mくらいの2頭のイノシシがこちらを伺っているではありませんか。「幽霊でなくイノシシかぁ・・」と安堵のため息が出ました。
それからは気を抜かずに眼をじっとにらみつけたまま、静かに静かに後ろに後退しつつ稽古場所に戻るとイノシシも安心したのか、そのうちいなくなりました。
道場の稽古では道場生にミットをもってもらい、スパーリングの相手になってもらいました。
こうして迎えた、昇段審査当日でしたが基本が終わった時点でスタミナがかなり無くなっていました。
型は何とかやり終えたという感じでした。組手ではスタミナが心配になり、ペース配分をした受け中心の組手になってしまいました。
組手本来の“最初から倒れても全力で行く”と言う主旨からは程遠い組手になってしましました。
20人終わった時点では立っているのがやっとでした。決して納得の行く組手ではありませんでした。
自己管理の甘さと精神力の弱さを充分に痛感させられた昇段審査会でした。
大石最高師範からは審査会終了後に「元気がなかったけれど、頑張っていたのが良かった」と、朝波師範からは「あと10kgやせなさい」と仰って頂きました。
本当に自分の到らぬところがよく分かり、今まで以上にまた一から頑張ろうと前向きのやる気が出て来たことは良かったと思います。
今後は極真空手を通じて、「人間力の向上と自己管理の徹底」を目標に今まで以上に稽古に励むと共に、何年かかっても滋賀県に極真空手のすばらしさを
広めていけるように努力精進していきたく思います。
最後になりますが、大石最高師範はじめ、芹沢事務局長、いつも親身になってご指導頂いている朝波師範、大石和美先生、松田先生、兵庫の米山先生、
岐阜の太田先生、安藤克己先輩、諸先輩方や同輩後輩たち、応援してくれた少年部のみなさん、そしていつも暖かい心で空手に理解をしてくれている家内に
心よりお礼と感謝を申し上げます。
押 忍
|